チームインタビュー20チーム目!!
夢源風人さんの4つ目の記事です!!

前半の3つの記事はチームの中のお話でした。
どまつりで長く過ごしていたらそこでのやり方が当たり前、全国共通のような錯覚に陥ってしまいがちになりますがそれが「井の中の蛙である」ということを痛感させられた感覚です。
こういう在り方、チーム運営の仕方があるのかと目から鱗とはまさにこのこと!と言わんばかりの違いがとても興味深かったです。
まだ前3つのインタビュー記事読んでない!という方は是非読んでみてくださいね♪♪
4. 100年続くチームのために ← イマココ
5. ぴとぅさんのSNS戦略とは
6. メタル鳴子制作秘話 + 演舞は〇〇〇
そんなわけで今回はチームの思想、理念、活動目的等のお話です。
どまっぷブログをご覧いただいている方の多くは東海圏の方々だと思います。
東海圏と言えばどまつりがあります。
どまつりは賞があり、多くのチームがそこでの受賞を目指して(それが目的でないにしろ)活動しています。
ぴとぅさんは賞を目指していません。賞のために活動していません。
そこにはどのような想いが込められているのか、というお話です。
今回のお話は「チームとはどうあるべきか」のようなお話です。

目次
1. 賞を目指さない理由

(前回の③スタッフは〇〇人以上!?の続きになります。)
ハッキリ言っちゃう
「賞とりたいって目的で入ってこようと思ってる人は、うちは賞を目指すためのチームではないので、別のチームさんのほうがいいと思います」 って最初に言ってたりするくらい、賞を目的に活動しているチームではないです。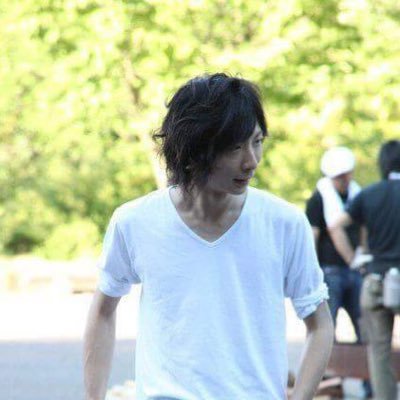

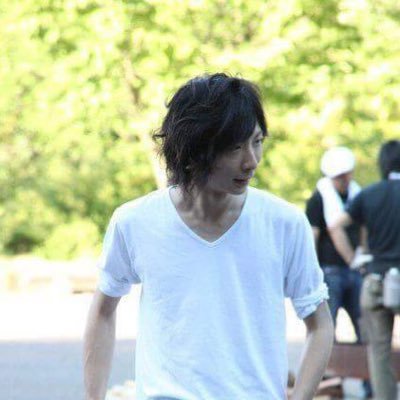

ーーーそれが一番いいですけどね。楽しみながら結果もらえました、が一番いいですよ。
どまつり圏外の人に言わせると、どまつりでファイナル進出できなかった時みんな泣き崩れるっていうのがおかしいとよく言われます。
僕らは逆にそれが普通なのですが、本来は「賞を狙う」ということよりもまず何より「楽しむ」「楽しませる」ということが先決ですよね。
大切なメンバーに勝ち負けを感じてほしくない
悪い意味じゃなくて、すごい殺気みたいなものが見えるときがある(笑) ファイナルに出られなかったりで悔しいのはわかるんですけど、 大切なメンバーに「勝ち」とか「負け」とか大好きなお祭りで感じさせるのは・・・何かちょっと・・・かなしいです(笑)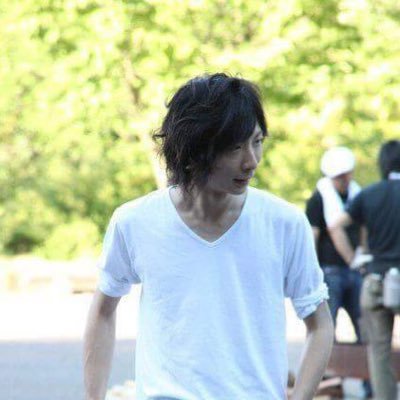
ーーーわかります。
最近だとテレどまつりの審査ブロックっていうのが発表されたんですけどよくあるのが、
「〇〇と同じブロックになってしまった!!」とか
「△△とは違うブロックだから良かった~」みたいな
意見がtwitterで出てくるんですよね。
それってそもそも表現をする場なのにやる前から勝ち負けの土俵に上がっちゃっているのはなんかなぁ・・・って思います。
「強い」「弱い」とか「勝ち」「負け」とか、そういった優劣みたいな中に大切なメンバーを入れたくないんです。 「今年は(ファイナル)行けなかったねー。でも、楽しかったねー。 観てる人に伝えたい思いは、きっと届いてるよ」 でいいのになーと。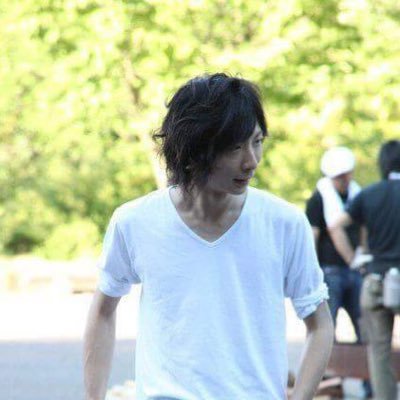
ーーーそうなんですよね。
どまつり前ってそういうところもあってめちゃくちゃピリピリするんですよね。
さっき言ってた「殺気」っていうのがまさにと言ったところです。
もちろんチームにもよりますけど賞を目指しているチームはみんな最後の追い込みを文字通り殺気立って、死ぬ気でやってる、といったところです。
指導する側もメンバーにアツいアツい檄を飛ばすようなシーンを目撃することもよくあります。

ーーー「賞」っていうひとつの目標に向かってみんなで頑張る、切磋琢磨し合うっていうところの楽しさはあると思ってます。
なので恐らくお祭りの楽しみ方っていうのが賞を目指すチームと賞を目指していないチームとで全く異なりますよね。
楽しみは高知でお客さんの前で踊ること
よさこい祭り(高知)は、お祭りの途中に、8/11の夕方頃に審査結果が発表されてるんです。受賞チームに電話と、公式サイトのHPで。 そして審査発表に関係なくよさこい祭りは21時頃まで続いていて。 審査というよりも、 高知で踊ること、お客さんの前で踊り続けることが楽しみになってるし、 そこでのコミュニケーションが思い出になってる。その楽しみ方の文化の違いなだけかなって思います。 勝ち負けがとか、優劣がとかさっき言ってましたけど、 だからといって「賞を目指してる人たちに、どうこう、、、」っていうのではなくて、 賞を目指して練習してきて、達成できた喜び、残念だった涙は凄くかっこいいと思っています。 そこまで打ち込めるものに出会えるって、素敵だなぁって思います。 うちのスタイルとは違いますけど、名古屋のチームさんのすごいところでもあるんだろうなあって思います。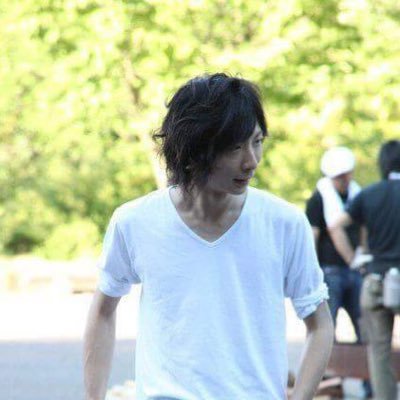
それに一緒だと思うんです。 うちみたいなチームも、どまつりさん地域の賞を目指すチームさんも。 「ひとつの目標に向かってみんなで頑張る、切磋琢磨し合うっていうところの楽しさ」や、 「燃え尽きる」というところは、賞うんぬんにかかわらず一緒なんじゃないかなと。 目的とするものが、目に見える結果なのか、目に見えない思いなのか、そこが違うだけで、 どちらも「目指してる過程でココロが動く瞬間」っていうのは同じようにある。 そんなココロが動く瞬間がたくさんたくさんあるというのが、”よさこいの魅力”だなってわたしは思っているので。


たとえば賞を目指して、賞を獲りたいから踊りたいんですってすごくシンプルですけど、 ぴとぅにいて何がしたいですか?って全員から同じ答えは返ってこないと思います。 みんながある程度自分でも考えないといけないんですよね。 そしてお互いがお互いを認めていないとうまくいかないですね。
2. 活動目的的なところ
目には見えない思いのつながり
ーーーということは、ぴとぅさんのチーム自体の活動目的っていうのは、さっき言っていた大きなくくりでは「よさこいを盛り上げたい」っていうことになるんですか?
「目には見えない思いのつながり」があって、 そしてよさこいを愛して高知に行くチーム。 そこから実際の活動の場面に掘り下げると、コンセプトを軸として持ちつつ毎年代表によってこんなチームにしたいっていうのは変わります。
必ずここに帰ってきます!
追手筋に入る時の光は明日への希望のよう。
よさこいに関わる全ての方に愛と感謝を込めて。#ぴとぅの高知2021#StayKochi#目には見えない思いのつながり pic.twitter.com/Z0HaSs9Gom— 夢源風人「まるまんてん」|大阪から高知を思う。 (@mugenkajipitwu) August 11, 2021
「メンバーと周囲の人の幸せをつなげていく」っていうのがあります。 活動全般でもそうですが、「見てくれる方とコミュニケーションをとれる演舞」を作るっていうのが一つ大きなものとしてあります。 あとは「100年続くチームのためにみんなで作っていこう」って伝えてます。
「いつでも帰れる場所、戻れる場所であり続けたい」 というのは、コアで関わったメンバーは特に思っています。 例えば9年間離れた人が今戻ってきたりとか、出産で離れたけど戻ってくるとか。 戻れるところがあるだけで心が安心するじゃないですか。 その場所を提供するっていうのも20年続いてきた今だから、チームの活動目的のひとつになってきてるなって思います。 かなみが言った「100年続くチーム」っていうのは、いつでも帰ってこれるチーム。 ちょっと何かでしんどくなった時に楽しかった頃にあったチームに戻ってくると、楽しかった頃にいた何人か残っている。それだけで生きる活力になるんじゃないかなと思っているので。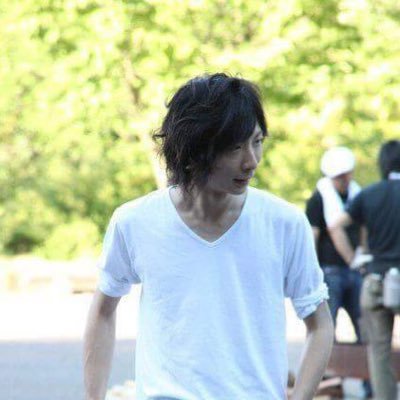


僕はあんまり人としゃべらないので役に立たないですけど、前にいた彼ら彼女たちが帰ってきたときに、かなみとかあきべー、はなやぶんちゃんとか10年以上チームにいる人たちがいることで安心する、そこで救われた、またやろうって思えたって人が何人かいるって聞きます。 そうやって活動していくことで、よさこいの母数が増えるじゃないですか。 そうすればよさこいがもっと広がるじゃないですか。 よさこいがもっと文化として深くなっていくじゃないですか、 そしてもっと興味を持つ人が増えていくじゃないですか、、、 プラスにつながっていくみたいな夢というか思いがあります。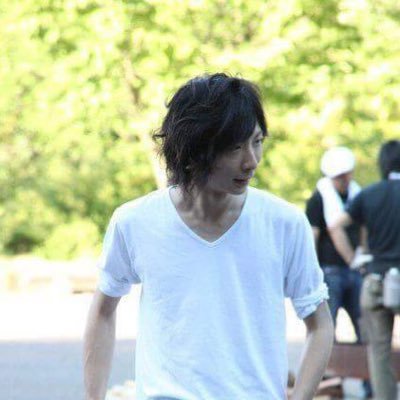


(10年以上在籍されている、いろんな人を救っているベテランの方々)
ーーーありがとうございます。その話すごいなあって思います、名古屋にはなかなかそうゆうのがないんで、それはすごく勉強になります。
これを記事にしたときに名古屋としては新しいチームのあり方っていうのが出てくると思います、名古屋はいま、新しいチームが出てきては、古いチームが無くなるっていうのがあるので。
ーーーーー
今回は以上です。
今回の話を聞いていて感じていたことは
「「勝ち負け」や「優劣」というものの中にチーム・メンバーを入れたくない」という考え
そして「いつでも帰ってこれるチーム」「居場所としてのチーム」というスタンスです。
特にこれらの考え方はどまつり圏内でもファミリーチームなどの在り方のひとつの回答であると感じました。
ファミリーチームは特に、
メンバーの若い子が成長して踊り盛りになってきた時に学生チームや社会人チームに行ってしまってメンバーが減ってしまう、
という問題を抱えています。
確かにメンバー減の痛手はありますがそこで賞などの結果を求めるのではなく、
チームを守り続けること
いつでも帰ってきていいよ、と温かく迎え入れてくれる居場所であること
そのようなチームであるべきなのかなって。
もちろん押し付けではありません。各々の在り方考え方があるのでそれらを否定するわけではありません。
ひとつ、こういう在り方もありですよねっていうところで今回のインタビューも参考になれば嬉しいです。
さて、次回のインタビューはぴとぅさんの
SNS戦略についてです。
こちらはどのようなチームでの参考になる、濃い濃い濃い内容です。




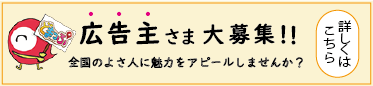
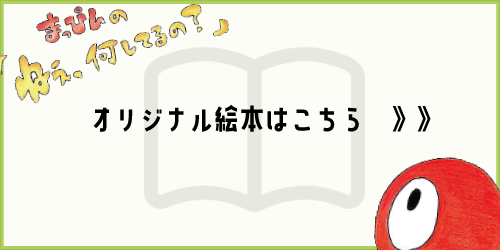
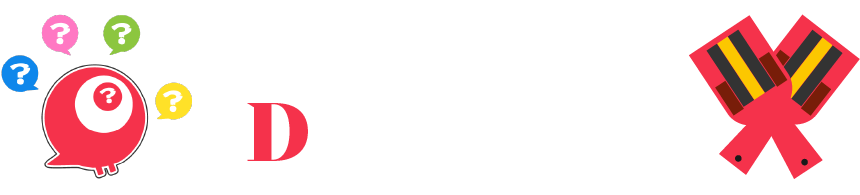
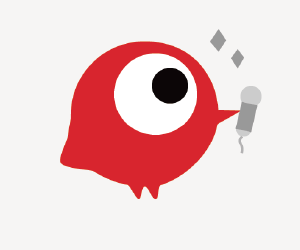
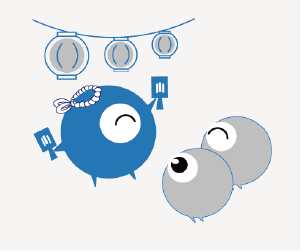
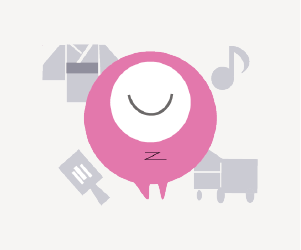
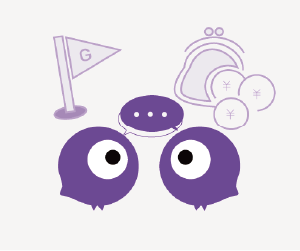

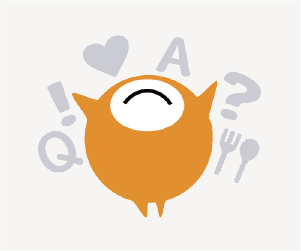








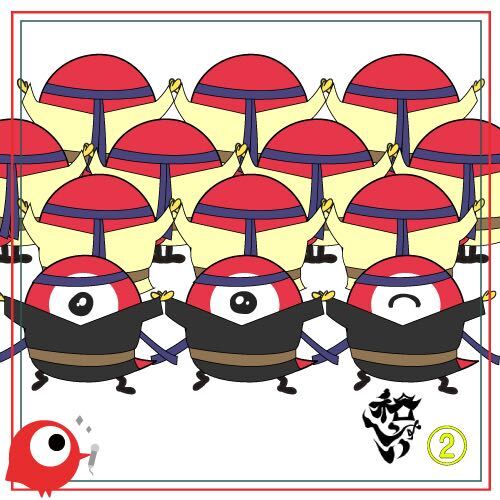
コメント